釣りキャンにこどもだけのまち〜逃げ場のない場所で得られるもの
- Tomoe Sakata
- 2024年8月8日
- 読了時間: 6分
更新日:6月13日
釣りキャン2024in大磯 小中学生6人と親元を離れてのキャンプが終わって1週間がたちました。
4泊5日でこども達と過ごすのは過去最長。気力体力持つかしらと心配でしたが、
楽しいことがたくさんあったので、あっという間に終了。
終わって3日間は寝不足からくる疲れと日焼けした肌を癒すのにぐったりしていましたが
ぐったりしながら子ども達とのやりとりがじわじわ思い出されました。(いい意味でね)
良い体験だったので何が良かったのか振り返ってみたいと思います。

キャンプというと自然と触れ合ったり、デジタルデトックスできるとか、協調性が育つとかいろんな目的を持って参加されてると思いますが、ファミリーキャンプでも体験できることはすっとばして、今回は「親から離れるメリット」に注目してみます。
まず参加したこども達のことをざっくり説明すると、小2から中1まんべんなく学年が混じっていて、ほぼ全員初対面。参加した目的も「釣り」「イカダづくり」「なんとなく?」とバラバラでした。
そして半分の3人は自分の気持ちや意見を言葉や態度で表現するタイプ、残る3人はその逆のタイプ。
釣りキャンという企画は、釣りをはじめ、カヤックやイカダづくりとテーマが「海」だったので、全ては海の状態次第、つまり計画なんてあってないようなもの。
海が穏やかなら釣りをして、荒れていれば陸でイカダ作って…という程度の計画でしたが、結果的には波も荒くならず、奇跡的に毎日釣りをしてイカダを作って、なんなら海水浴もしてと、海でのアクティビティを存分に楽しむことがきたんです!
「たった6人、でも個性あふれる6人、スケジュールは海次第」
これが今回の釣りキャンを楽しくしてくれました。

では今回のおもしろポイント別に振り返ってみます
1.何をするか変更できる余白がある故、大事なのは「交渉力」
2.釣れない釣りを楽しむ「ポジティブ力」
3.全体を見てバランスをとって前に進めていく「俯瞰する力」
4.逃げられない環境でどう楽しみをみつけるのか?

1.何をするか変更できる余白がある故、大事なのは「交渉力」
親ではない大人に「自分はこうしたい」と主張することって、できる人できない人がいると思いますが、できたほうが絶対良いよね。普段こどもDIY部でやっている「じゆう工作」も「こどものまちをつくろう」も、「自分はこうしたい」っていう意思を示さないと全然面白くない。
冷静に考えて、何十歳も離れた古臭い人間が良かれと思ってやってることなんて、子どもにとって面白くないに違いない。こんなことをしたらもっと楽しいよ!こうしたいよ!と交渉することはとっても大事です。
ただ声大きく主張するのが苦手な子がいるのも事実。声が出せなくても結果的に交渉することが成功すれば良いので、相手の話をじっくり聞いて「相手はこうしたいんだ」を理解して自分の主張を交えて「じゃあこうしようよ」と冷静に伝えるところからできた子が最強でした。
難しいのですぐには無理でも、成長と共にできるように小学生のうちからこの考え方に慣れておくと絶対役に立つだろうな。
今回は声の大きい3人がとにかく積極的にやりたいことを言い、その中で面白そうなものがあれば残りの3人がのっかり、実現していくというパターンでした。変えられる成功体験になったと思います。

↑見かねて手伝ってくれた地元の方。釣りの時だけじゃなく、歩いているだけでも、大磯の人がよく話しかけてくれる。東京だったら不審者扱いだけど、こどもたちも嬉しそうに話すその違いはどこにあるの?
2.釣れない釣りを楽しむ「ポジティブ力」
「年々魚が釣れなくなってる」という話は釣りをしない人でも耳にしたことあると思います。今回の舞台となった大磯も、日中釣りに行ってもそんなに釣れない印象でした。なのでせめて朝か夜になら何か釣れるだろう!ということで、泊まり込みキャンプにしました。
私自身も釣りをはじめて1年ほどの初心者ということもあり、釣り自体は「何が釣れても楽しい。食べられればなお嬉しい」くらいの感覚で釣りに行っています。
なぜなら釣った魚をバケツに入れてその様子を観察するだけでも楽しいですし、釣れないながらも餌に寄ってきた魚を観察するのも楽しい。
さらに釣りという共通の話題があるので、周りの人と話すきっかけがたくさんあります。
隣のお兄さん達のしかけを借りて釣ってる強者もいました。
「釣りは思い出作り」と割り切ると、釣果にこだわらず楽しめる姿がよかったです。

3.全体を見てバランスをとって前に進めていく「俯瞰する力」
自己主張をすることは先の交渉力と混同しそうですが全然違います。「自分のやりたいことを主張するだけ」は困ります。
自分で使った食器は片付ける、読んだ漫画を片付ける、自分の洗濯物は自分で干す。親がいないのだから自分でやるべきなのにやらないので、ちゃんとやった子が待たされるという迷惑な状況が毎日何度も起きる。
やらない子に対して大人が注意をする→ちゃんとやっている子が代わりにやる→やるべき人がやらない という悪循環が発生。
大人の社会でも似たようなことは起きてると思うんですけど、こどもの社会では黙って周りをフォローする人への感謝も対価もなく、我慢するだけになりがちで不公平この上ない。全体を見て前に進むために黙って進んで物事をやる人に対しての評価が低い。そこをもっともっと評価したら面白いことが起きるだろうなと気づいたんです。
実際「こどものまちをつくろう」でまちの中心機関である「議会」に「どうしたらまちが良くなるか」という視点を持てる子が来てくれると、その年は面白くなるんですよ。

4.逃げられない環境でどう楽しみをみつけるのか?
釣りしたい子、イカダを作りたい子、なんとなく参加した子、興味の方向はバラバラの6人の参加者が、そんなに興味ないけど、みんなで行動しなくてはいけないが故やっているうちに、他の子の熱心さに引っ張られるように興味を持って釣りをしていたのは面白かったです。逆に釣りをしたくて参加したのに、糸がリールにからまるし、しかけはぐちゃぐちゃになるしで頭で思っていたより難しくて嫌になっちゃった子もいました。
親と一緒だと「これいやだ」と言ったらじゃあ別のことをしようか、ってなりがちですが、勝手な行動ができないこどもだけの釣りキャン。目の前のことに嫌でも取り組むしかない。
「逃げられない環境でどう楽しみをみつけるのか?」という変化のポイントを見ることができたのは大きかったです。
保護者が入れない「こどものまちをつくろう」というイベントは「身近でできる小さな留学体験」という点に一番の価値があります。こどもが「つまんない」って電話してきても放っておくくらいの態度で送り出すべき場所です。その先を自分で切り開けるかが成長の鍵だからです。
予想していませんでしたが、今回の釣りキャンも同じような状況が生まれました。
きっと6人のキャラクターが見事にバラバラだったからだと思います。
一緒に結託して目標に向かう楽しい時間もあったし、喧嘩やトラブルもあったけど、たった5日間とは思えない盛りだくさんの時間になりました。
釣りキャンを通して親が関わらない時間を持つことの大事さを改めて体験することができました。
また来年もできたらいいね。

こどもDIY部の小学生・中学生を対象にしたサマーキャンプを3泊4日、場所は大磯で行います。サーフィン、釣り、イカダづくりと、夏休みに海辺のまちでの暮らしを体験をしてみませんか?
2025年釣りキャンの参加者を募集しています。
詳細はこちらのページへ





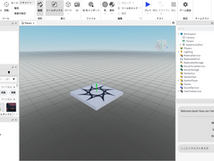







コメント